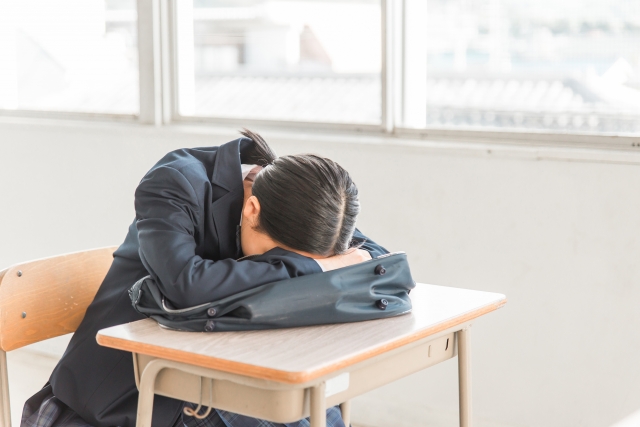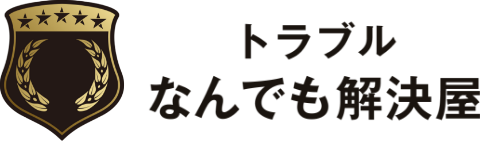2025.04.24
2025.04.24
家族トラブル
お子様に関するトラブル
いじめトラブル
非行に関するトラブル
子供がいじめられていると気づいたときの正しい対応

【はじめに】
「もしかして、いじめられているかも…」
子どもの変化に気づいても、どう声をかければいいのか、どう行動すればいいのか分からない――
そんな親御さんは少なくありません。
本記事では、いじめの初期兆候から、絶対にやってはいけない対応、
そして家庭での支え方・学校や第三者の関わり方まで、
トラブル解決の専門家が実例を交えながら徹底的に解説します。
- いじめのサインはどこに現れる?
- 親の対応ひとつで状況が悪化することも
- 学校に相談すべき?それとも外部に?
- 証拠がなくても動ける方法とは?
- 誰にも知られず、解決に動く手段も存在する
大切なのは、「気づいたとき、どう動くか」です。
一人で悩まず、この記事から最初の一歩を踏み出してください。
 元木
元木
【1. 子どもがいじめに遭っているサインとは?】
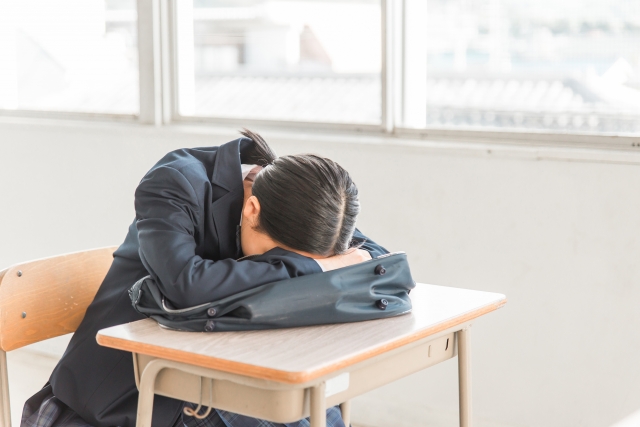
いじめは、必ずしも「あからさまな暴力」や「はっきりした悪口」として現れるわけではありません。
特に最近のいじめは、見えにくく・気づきにくい形で進行しているケースが多く、
親や教師が発見しづらくなっています。
以下は、私たちが現場で確認してきた“いじめの初期サイン”です:
●生活・行動の変化
- 急に学校に行きたがらなくなる(朝だけ具合が悪い)
- 食欲がなくなる/逆に過食傾向になる
- 夜眠れない、寝付きが悪くなる
- スマホやゲームへの没頭が極端に強くなる
- 以前好きだったことに急に興味を示さなくなる
●性格・表情の変化
- 些細なことで怒るようになる
- 無口になる、会話を避ける
- 常に不安そうな表情をしている
- 「自分なんて」「消えたい」など否定的な言葉が出てくる
●身体の異変
- 原因不明の腹痛や頭痛を訴える(=ストレス反応)
- 制服や持ち物の紛失・破損が増える
- 顔や体に小さな傷やアザが繰り返し見つかる
特に「体の不調を理由に学校を休みたがる」「スマホを見たあとに明らかに落ち込んでいる」といったサインは、
見えないいじめ(SNS・LINEグループなど)の可能性があります。
早期に気づけるかどうかは、親の“観察力”と“違和感を信じる力”にかかっています。
【2. まず親が取るべき初動対応】

いじめかもしれない、と感じたとき、親が最初に取る行動がとても重要です。
この初動対応によって、子どもが「味方がいる」と思えるか、「もう誰にも言えない」と感じるかが決まってしまいます。
●①“問い詰めない”を鉄則にする
「何かされたの?」「誰にやられたの!?」と問い詰めると、
子どもは“守り”に入ってしまい、本当のことを話さなくなります。
●②まずは“違和感の共有”から始める
「最近ちょっと元気ないけど、何かあった?」
「ママ(パパ)はちょっと気になってるだけなんだけど…」
というように、“見守っているよ”というサインを送ることから始めましょう。
●③話さなくても“態度で味方であること”を伝える
本人が話せない場合は、それでも構いません。
ご飯を一緒に食べる、いつも通りに接する、小さな会話を大切にする――
そういった“日常の安心感”が、子どもの心をほどくきっかけになります。
私たちの支援現場でも、いじめ問題の多くは「最初の親の関わり方」がその後の分岐点になっています。
焦らず、否定せず、守る姿勢を見せ続けることが、信頼の第一歩です。
【3. いじめ対応で親がやりがちなNG行動】

いじめを疑ったとき、良かれと思ってやってしまう行動が、
かえって子どもを追い詰めてしまうことがあります。
以下のNG対応には特に注意が必要です:
●①「なんで言わなかったの?」と責める
子どもは、“言えなかった理由”が必ずあります。
責められたと感じた瞬間、今後一切話してくれなくなることもあります。
●②「そんなの気にしないで行けばいい」などの軽視
「気にしない」は、“気にしてる自分が悪い”というメッセージになります。
親の中では励ましのつもりでも、子どもには“理解してもらえなかった”と伝わってしまうのです。
●③「先生に全部言ってあげるから!」と勝手に動く
本人の同意なしに学校へ連絡したり、相手の親に接触するのは極めて危険です。
加害側に警戒され、いじめが“見えにくい形”に変化したり、
子どもが“裏切られた”と感じる可能性もあります。
重要なのは、「味方である」という安心感と、「一緒に考える」という姿勢。
親の正義感や怒りが前に出すぎると、かえって状況が悪化することを忘れてはいけません。
【4. 子どもとの信頼関係を守る会話術】

いじめの問題において、子どもが本音を打ち明けられるかどうかは、
親との信頼関係にかかっています。
これは「仲が良いかどうか」とは違い、“話しても否定されない空気”があるかどうかが大きなポイントです。
以下は、現場でもよく使われている信頼を守るための会話テクニックです:
●①「聞きたい」ではなく「知りたい」に変える
- 「いじめられてるの?」ではなく、「最近、つらいことあった?」と“状態”を聞く
- YES/NOで答えられない質問のほうが、自然な会話につながりやすくなります
●②“本人の視点”に寄り添う言葉を使う
- 「そんなの気にすることない」ではなく、「それは嫌だったね」「よく我慢してたね」と感情に共感する
- “解決”よりもまず“共感”を優先する姿勢が重要です
●③話してもらえなかったときは、責めない
- 話してくれない=信頼がない、ではありません
- 「いつでも話したくなったら聞くからね」と“逃げ場”を作ることが、結果的に安心につながります
子どもは、意外と親の表情や言葉の選び方に敏感です。
正しい言葉選びが、心のドアを開くカギになります。
【5. いじめが学校で認められないときの動き方】

「学校に相談したのに動いてくれない」「“いじめではない”と言われてしまった」
そんな声が私たちのもとにも数多く寄せられます。
実は、学校がいじめに対応できない背景には、いくつかの“制度的な壁”があります:
●学校が対応しづらい主な理由
- いじめの定義が曖昧で、学校側が判断に迷う
- 加害者の親への配慮や、学級崩壊のリスクを恐れて動きにくい
- 証拠が乏しいと「認識していない」として処理されやすい
- 教師個人の力量により対応に大きな差がある
では、学校が動かないとき、どうすればいいのか?
●①“記録を残す”という行動が鍵
- 日付・状況・会話内容・持ち物の変化などをノートに記録
- メールや連絡帳でのやりとりも保存
→これらが第三者が動く際の「証拠」になります
●②“教育委員会や第三者相談窓口”も視野に入れる
・直接学校ではなく、上部機関に事実を報告することで、別の視点からの調査が動くことがあります
●③必要に応じて、学校以外の調査手段を使う
- SNSや通学ルートでの行動観察など、学校の外から見えるいじめの実態もあります
- 私たちは、本人に気づかれずにそうした状況把握を行うことが可能です
「学校が頼れないから仕方ない」と諦めるのではなく、
別のルートで事実を掴み、必要な対処を進めることが大切です。
【6. SNS・スマホいじめの見抜き方と対策】

現代のいじめは、教室の中だけでは終わりません。
LINE・Instagram・TikTok・ゲームチャットなど、
スマホを通じた“見えないいじめ”が急増しています。
特に多いのは次のようなケースです:
●SNS・スマホいじめの例
- グループLINEで仲間外れにされる/既読スルーで無視される
- 裏アカウントで悪口や画像を拡散される
- 「◯◯はキモい」などの投票やランキングで晒される
- ネット上でのトラブルを現実のいじめに結びつけられる
こうしたデジタルいじめは、親や教師が気づきにくい一方で、
子どもの心に大きなダメージを与えます。
●対策①:スマホの利用履歴やSNSの動きを定期的に確認
- 見せてもらうのではなく、「本人の了解を得た上で一緒に見る」スタンスがベター
- 時間帯ごとの使用傾向や“特定のやりとり直後の情緒変化”にも注目を
●対策②:裏アカ・捨て垢・メッセージ削除にも注意
- 本人に見せられないアカウントがある可能性を前提に考える
- 証拠が消される前に、必要な画面のスクリーンショット保存を
●対策③:専門家によるスマホ調査やSNS監視も選択肢
- 家庭では把握しきれない内容も、専門的な技術で発見・記録が可能です
- 本人に知られずに調査する方法もあり、対応の第一歩として有効です
「スマホに詳しくないから見られない」ではなく、
今のいじめは“スマホの中”にこそあると認識し、行動することが何より重要です。
【7. 証拠がない・子どもが話さないときの調査法】

「いじめを疑っているけど、証拠がない」
「子どもが何も話してくれない」
このようなケースでは、親が動きたくても“動けない”状態に陥ってしまいがちです。
しかし、いじめの実態は目に見えるものだけではありません。
そして証拠がないからといって、何もできないわけではありません。
●調査で判明したケースも多数
- 通学路での無言の囲い込み(言葉はないが明らかな威圧)
- 学校内での持ち物の破損・盗難(本人が黙っていた)
- SNS上での匿名誹謗中傷(裏アカによる晒し行為)
- 部活内での無視・陰口(教師は気づかず放置)
こうした「目撃されない」「記録に残らない」いじめこそ、
家庭や学校からは見えにくいのです。
●第三者による調査が有効な理由
- 本人に知られずに周囲の状況を確認できる
- 学校の外(通学・放課後・SNS)も調査範囲に含められる
- 事実をもとに、学校や加害者側への“対策資料”を整えられる
私たちトラブルなんでも解決屋では、いじめの実態を可視化するために、
- 張り込み/聞き込み/SNS解析/学校周辺調査 など、ケースに応じた調査方法を組み合わせて対応しています。
「見えないから動けない」のではなく、
“見えるようにする”ことで解決の第一歩を踏み出せるのです。
【8. 相手側への介入と注意点】

いじめの加害者やその親に対して、「直接注意してやりたい」「事実を突きつけて謝らせたい」と思う親御さんも多いでしょう。
しかし、感情に任せた介入は、事態の悪化を招く危険性があります。
●リスクのある直接介入
- 子ども同士のトラブルが、親同士の“別のトラブル”に発展
- 加害者側が逆に「被害を受けた」と主張してくるケースも
- 本人への報復や、いじめの“隠蔽化”が起こる可能性も高い
●安全な介入方法とは?
- まずは客観的な証拠(記録・調査結果)を確保する
- 学校や第三者機関を通じた、冷静な対応が基本
- 直接の接触は避け、法的な専門家や支援者のサポートを得る
●私たちがサポートできること
- 加害者側との“間接的な接触ルート”を構築
- 必要に応じて、弁護士と連携しての内容証明や交渉対応
- 本人への報復や“二次被害”を避けながら関係遮断を進行
大切なのは、「子どもを守ることが目的」であって、感情のぶつけ合いではないということ。
冷静に、でも確実に。 そのためには、第三者の存在が大きな力になります。
【9. 家庭のメンタルケアと環境づくり】

いじめを受けている子どもが回復していくには、“安心できる家庭環境”の存在が何より重要です。
学校や社会で傷ついた心は、まず家の中で癒されなければ前に進めません。
●回復のための家庭づくりのポイント
① 無理に元気づけようとしない
- →「頑張って」「大丈夫」は、プレッシャーに感じることもあります
- →それよりも、「そばにいるよ」「今日はどんな一日だった?」と寄り添うことが大切
② 生活リズムを“親が”整える
- →昼夜逆転や引きこもりにつながらないよう、食事や起床を家族が先導
- →子どもだけに「ちゃんとしなさい」と言わず、親も一緒にリズムを整える姿勢を見せる
③ “楽しい話題”を日常に混ぜる
- →学校やいじめの話ばかりでは、心が塞がってしまいます
- →何気ない話題や家族との笑顔の時間を増やし、“普通の生活”に戻る準備を少しずつ進めましょう
子どもが話せなくても、笑わなくても、“居場所としての家”がそこにあることを伝えること。
それが、メンタルの再生において最も大きな支えになります。
【10. 学校・支援機関・専門家、それぞれの役割】

いじめ問題を解決するためには、「誰に」「何を」相談すべきかを冷静に見極める必要があります。
学校だけに頼っても限界がありますし、逆に家庭だけで抱えるのもリスクが高い。
だからこそ、それぞれの役割と得意分野を把握し、使い分けることが大切です。
●学校の役割
- 校内での対応(担任・学年主任・スクールカウンセラーなど)
- 学級内の指導、加害者への対応、教職員会議での共有
- 問題が明るみに出れば一定の対応義務が生じる(「重大事態」扱いなど)
→【注意点】証拠や状況次第で、曖昧な対応や責任回避がされることも。
学校任せにしすぎず、記録を残して親側からも動きを監視する必要があります。
●教育委員会や行政窓口
- 第三者視点で学校の対応をチェック
- 学校では進まなかった問題に対し、外部調査の要請ができる
- 相談記録を残すことで、学校へのプレッシャーにもなる
→【注意点】動き出しが遅い/形式的な対応になる可能性があるため、早急な対処には不向き。
●民間・専門家チーム(私たち)
- 本人に気づかれず、外からの調査・分析が可能
- 証拠の取得や、親子間の対話支援、加害者側への介入も含めて“現実的な対応”ができる
- 学校や加害者側との交渉も視野に入れた計画が立てられる
→【強み】スピード感、秘密保持、対応範囲の広さ。
何より、「誰にも知られずに動ける」ことが最大の安心材料になります。
【11. 私たちが動けること。秘密裏の対応と実績】
「証拠がないけど、明らかに子どもが変わった」
「学校も周囲も信じてくれない」
「どうしていいかわからない」
そう感じた時こそ、私たちが動くタイミングです。
トラブルなんでも解決屋では、学校や家庭では対応しきれない“見えないいじめ”を、秘密裏に調査・分析・対応する専門チームを構成しています。
●私たちが対応できること
- 本人や加害者に知られずにいじめの実態を調査(通学ルート・放課後・SNSなど)
- 証拠を確保し、学校・加害者側への間接的な対応を支援
- 家庭内での親子関係再構築、本人の心理ケア・自信回復サポート
- 場合によっては、法的手段を含めた再発防止策の提案も可能
●“どこにも言えない”という方でも大丈夫
- 365日・24時間対応
- 完全匿名・秘密厳守
- 相談だけでもOK。「今、何が起きているか」を一緒に整理するところから始められます
いじめ問題は、放置すればするほど根が深くなり、本人の心をむしばんでいきます。
でも、最初の一手が早ければ早いほど、回復も再出発も可能です。
誰にも相談できずにいるなら、まずは私たちに話してみてください。
声をあげること。それが、子どもを守る最初の一歩になります。
一覧へ戻る