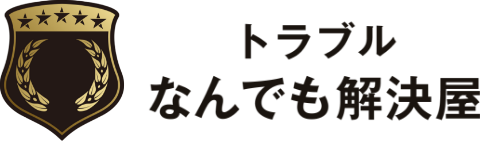2025.04.22
2025.04.22
家族トラブル
お子様に関するトラブル
いじめトラブル
ひきこもりのお悩み
交友関係
いじめている
いじめられている
対処方法
子供の引きこもりが長期化する本当の原因

【はじめに】
「そのうち元に戻るだろう」
「思春期だから仕方ない」
そう考えていたご家庭で、引きこもりが1年、2年と続いているケースは少なくありません。
実際に、私たちトラブルなんでも解決屋には、
「誰にも相談できず、ここまで来てしまった」という親御さんからのご相談が増えています。
この記事では、以下のような観点から“引きこもりの本質”と“解決の糸口”を専門的に解説していきます:
- 子供が引きこもりになる本当の背景と心理
- 家庭内で親が見逃しがちなサイン
- 学校や支援機関では限界のあるケース
- 本人と接触できない状態でもできるアプローチ
- 誰にも知られずに進められるプロの調査と介入
最後には、私たちがどのようにチームで対応し、家庭だけでは難しい問題に“秘密裏に”動けるのかをご紹介します。
大切なのは、「気になる段階で動く」ことです。
どうか、ご家庭の未来を守る一歩にしてください。
 元木
元木
【1. 引きこもりとは?よくある誤解と現実】

「学校に行かなくなっただけ」「そのうち落ち着くだろう」――
子供の引きこもりに直面したとき、多くのご家庭が最初に抱くのはこうした“楽観的な予測”です。
しかし実際の現場では、時間が経てば経つほど、状況は悪化する傾向があります。
問題の根本が解決されないまま日常が静かに崩れていき、
気づけば家族関係も会話も断絶されている…そんなご相談が後を絶ちません。
引きこもりとは、単に「家から出ない状態」を指すのではなく、
- 社会的な接触を避ける
- 家族との関係すら閉ざす
- 本人の中で現実との断絶が進行していく
という“心理的孤立”の状態を含むものです。
また、「引きこもり=不登校の延長」と捉える人もいますが、
高校・大学・就職後のタイミングで突然発症するケースも多く、
年齢や環境に関係なく起こる可能性があります。
つまり、引きこもりとは「一過性の怠け」ではなく、心の防衛反応としての“逃避”が慢性化した状態なのです。
【2. 子供が引きこもる本当の原因とは】

親から見れば「きっかけが分からない」「何が不満なのか見当がつかない」と感じることが多い引きこもり。
しかし、その背景にはいくつかの共通した“原因の構造”があります。
●過去の挫折やトラウマ
- 学校でのいじめや仲間外れ
- 受験や部活などでの失敗体験
- 進学・就職のミスマッチ
●自己否定や自信喪失
- 周囲と比べて劣等感を抱いた
- 「期待に応えられない」と思い込んでいる
- 家庭内で認められた経験が少なかった
●家庭内の圧力・関係悪化
- 親の過干渉や過期待
- 兄弟姉妹との比較
- 会話が表面的で本音が話せない
●環境依存(ネット・ゲーム・昼夜逆転)
- 現実世界よりも安全で心地よい仮想空間に逃避
- 生活リズムの乱れによる社会不適応
多くの場合、これらの要因が複雑に絡み合って引きこもりが起きているため、
「ひとつの理由を見つけて取り除けば解決する」という単純な問題ではありません。
また、本人自身も「なぜ自分がこうなっているのか分からない」と感じていることがほとんどで、
無理に話を聞き出そうとしても逆効果になる場合が多く見受けられます。
【3. 家庭で見逃されやすい初期サイン】

引きこもりは、ある日突然始まるものではありません。
ほとんどのケースでは、初期の小さな変化が積み重なって、ある日限界を超える形で発症します。
以下は、私たちが実際のご相談の中で見てきた「見逃されやすい初期サイン」です:
●生活習慣の乱れ
- 朝起きられない、夜型になっていく
- 食事の時間が不規則になり、1人で食べたがる
- 入浴や身だしなみに無頓着になる
●会話・感情の変化
- 親との会話が極端に減る、返事があいまいになる
- 感情の起伏が激しくなる(すぐに怒る・泣く)
- 「どうせ自分なんて」といった自己否定の言葉が増える
●学校や外出への違和感
- 登校渋り、体調不良を訴える頻度の増加
- 「今日は行かなくてもいいかな」と軽い逃避発言が出る
- 休日に一歩も外出しなくなる
●デジタル環境への依存
- スマホやゲームの使用時間が極端に長い
- SNSでの人間関係に依存し始める
- 現実との接点が減り、“画面の中”が主な居場所になる
これらの兆候が複数重なる場合、すでに引きこもりの予備段階に入っている可能性があります。
重要なのは、「気になるけど、様子を見よう」と放置しないこと。
早期にアプローチすれば、深刻化する前に軌道修正できる可能性は十分にあるのです。
【4. 実際にあった引きこもり家庭の相談例】

私たちの元には、さまざまな背景を持ったご家庭からの相談が寄せられています。
ここでは、実際にあった相談の一部をもとに、引きこもりの発生から対応までの流れをご紹介します(プライバシー保護のため一部改変あり)。
●ケース①:高校中退後、半年以上部屋から出ない息子
母親からの相談。「高校を中退してから昼夜逆転し、会話がなくなった。最初は“休ませてあげよう”と思っていたが、気づけば半年が経っていた」
調査を通じて、本人がネット掲示板で「社会復帰が怖い」「何もできない自分は価値がない」と書き込んでいることが判明。
親には何も言えず、孤独と自己否定に苦しんでいた。
当社の支援スタッフが段階的に本人と接触を図り、まずは家の外に一緒に出ることからスタート。
その後、通信制の学校との連携により、新しい目標を設定して社会復帰を目指す段階へ。
●ケース②:大学に入学後すぐ引きこもりに。原因は“失敗”への恐怖
父親からの相談。「優秀だった娘が大学に入ってすぐ、授業に出なくなり、部屋から出なくなった」
本人は、初めての孤独・環境変化・学業不振から、“完璧でいなければいけない”という重圧に潰され、すべてを遮断するようになっていた。
当社は、親からの聞き取りをもとに本人の心理状態を分析し、段階的に外部カウンセラーと連携。
親子間の会話スクリプトも作成し、家族関係の再構築も支援。
結果、本人の自己肯定感を取り戻すことで、再スタートが切れた。
こうした事例に共通しているのは、「時間が経てば経つほど、本人が“戻れない”と思い込んでしまう」ということ。
だからこそ、早期の情報収集と、第三者の冷静な関わりが極めて重要になります。
【5. 放置すると起きる家庭への深刻な影響】

引きこもりの問題は、単に「子どもが家にこもっている」だけに留まりません。
放置すれば、本人だけでなく家庭全体に大きなダメージを与えます。
●親子関係の崩壊
- 親が口出しすればするほど本人は壁を作る
- 話し合いがすべて“喧嘩”になる
- 家の中で無言・無視・威圧的な空気が続く
●経済的・生活リズムへの影響
- 親が仕事を辞めて付き添い生活になる
- 医療費やサポート費が長期化して負担に
- 生活全体が子ども中心に回り、他の家族にもしわ寄せ
●家庭内暴力・物への依存
- 「引きこもり+キレやすさ」が合わさるとDV化することも
- アルコール・過食・ゲームなどへの依存が悪化
- 部屋のゴミ屋敷化、衛生環境の悪化
●兄弟姉妹への影響
- 比較され、プレッシャーを感じる
- 親の関心が引きこもりの子に集中し、疎外感が強まる
- 家庭全体が“息が詰まる空気”になり、別の問題を誘発
「様子を見よう」と思っていた数ヶ月が、取り返しのつかない数年になる。
それが引きこもりという問題の恐ろしさです。
そして、誰も悪くないのに、家庭が静かに崩れていく――そんな現実を私たちは何度も見てきました。
【6. 子供が親と話せなくなる心理構造】

「何を聞いても答えてくれない」
「声をかけると嫌な顔をする」
そうした状態に苦しむ親御さんは多いですが、その背後には明確な“心理構造”があります。
●①防衛反応としてのシャットアウト
本人にとって、家族との会話は“責められる場”に変わっています。
何を言っても「ちゃんとしなさい」「そんなことではダメ」と否定される――そう思い込んでいる状態です。
だからこそ、「話せば傷つく」という自己防衛で、会話そのものを遮断します。
●②“失望させた”という罪悪感
本人が引きこもってしまったことを、実は一番気にしているのは本人自身。
「親をがっかりさせた」「こんな自分なんて話す資格もない」――
そう思っているからこそ、向き合うことができなくなっているのです。
●③現実逃避の快適さ
“話せば現実に戻される”
引きこもりの子どもにとって、会話=現実との接続です。
今の自分にとって都合の良い仮想空間や無言の生活は、無意識のうちに“安全地帯”になっています。
つまり、親との会話がないのは「冷たいから」「無関心だから」ではなく、
傷つきたくない、責められたくない、失望させたくない――その思いの裏返しなのです。
この心理構造を理解しないまま「話しかけ続ける」「問い詰める」と、さらに心の扉は閉ざされてしまいます。
だからこそ、私たちのような第三者が“家族ではない立場”からそっと介入することが重要になるのです。
【7. 学校や支援機関で対応しきれない理由】

「まずは学校に相談しよう」「市の引きこもり支援センターに頼ればなんとかなる」
そう考えるご家庭も多いですが、実際には制度や体制の限界で対応しきれないケースが数多くあります。
●学校の対応の限界
- 担任やスクールカウンセラーの介入には限界がある
- “定期的な接触”が途切れると対応自体がストップする
- 本人が拒否すれば、動く手段がなくなる
- 「学校に来させる」ことが目的化してしまい、本人の本音に触れられない
●公的支援機関の限界
- 予約が取りづらく、初回面談まで数週間~数ヶ月
- 支援員が数回話して終わり、継続的な関わりがない
- “親の意向”より“本人の意思”を優先するため、動けないことも多い
- 深刻なケース(家庭内暴力や無断外泊など)は対象外とされることも
また、支援が制度的に“本人の同意”を前提としている場合、
本人が動かない限りサポートに入れないという事実もあります。
つまり、「親としては何とかしたいけど、動いてもらえない」という状況が続いてしまうのです。
私たちのもとには、「行政にも学校にも相談したけど、結局どうにもならなかった」という方々が多数訪れています。
制度に頼り切れない“空白の領域”を埋められる存在が、今の社会には必要なのです。
【8. 本人と接触できないときのアプローチ法】

では、「話しかけても無視される」「そもそも部屋から出てこない」
そんな状態の中で、どのようにアプローチすればいいのでしょうか?
私たちは、これまで数百件を超える引きこもり案件の中で、
本人と直接会話ができない状態から関わりを築く方法を確立しています。
以下は、その一部です:
●段階的・間接的アプローチ
- 最初は家族からの情報をもとに、本人の状態を分析
- 直接接触ではなく、本人のSNSやオンライン活動を調査
- 家族向けに“本人が警戒しない関わり方”のアドバイスを提供
- タイミングを見計らって、手紙・小さな物のやり取りから開始
●信頼形成の“入り口”を見極める
- 本人の趣味や興味関心(ゲーム・アニメ・音楽など)から入り口を作る
- 年齢や性格に合わせて、接触するスタッフのタイプを調整
- 共通項を意図的に提示し、“敵ではない”という印象を与える
●“話す”より“安心させる”を優先
- 最初は「話そう」ではなく「一緒にいる」「見守る」だけでOK
- 本人が心を開くまで、絶対に急かさない
- 一度でも“話してよかった”という実感を持てれば、次の扉が開く
このような“間接ルート”を丁寧に積み重ねることで、
本人が「動いてみようかな」と思える環境をつくることが可能になります。
無理に引っ張るのではなく、本人が自分の足で一歩踏み出せる土壌を整える――
それが、私たちが大切にしているスタンスです。
【9. プロの調査・支援でできること】

私たちは、引きこもりの問題に対して「ただの調査会社」ではなく、問題解決に向けた総合支援チームとして動いています。
●できること①:本人の“今”を正確に把握する
- 部屋の外に出ていないか、誰かと連絡を取っていないか
- SNSやオンライン上での行動や交友関係を調査
- 実は深夜に外出していた、ネットでトラブルを抱えていた…など、“家族が知らなかった事実”を明らかに
●できること②:親御さんだけでは届かない接点をつくる
- 本人のタイプや状況に合ったスタッフが、段階的に関係構築を開始
- 本人に気づかれずに環境を整えるサポートも可能
- 手紙・SNS・偶然の出会いなど、本人に合わせた接触ルートを構築
●できること③:家庭再建のサポートまでトータルで対応
- 親との会話スクリプトを作成し、関係修復を支援
- 必要に応じて、専門のカウンセラーや進路支援スタッフが連携
- “引きこもり脱出後”の進学・就労・居場所づくりまで対応可能
私たちが提供するのは、“一時的な声かけ”や“気持ちの傾聴”ではありません。
本人と家庭の両方を“動かすための計画的な支援”です。
「何から始めればいいかわからない」「このままではまずい」
そう感じた今が、動き出すタイミングです。
【10. 解決に必要な“家庭の再設計”とは】

引きこもりの問題を根本から解決するためには、本人だけでなく、家庭そのものを見直すことが欠かせません。
なぜなら、引きこもりは「個人の問題」ではなく、「環境の結果」として生じている場合が多いからです。
以下は、私たちが実際の支援の中で行っている“家庭の再設計”の一部です:
●①親の関わり方の見直し
- 励ますつもりがプレッシャーになっていないか
- 「正論」が本人にとって攻撃に聞こえていないか
- 「こうあるべき」で縛ってしまっていないか
私たちは、親御さん向けに“伝わる言葉選び”や“避けた方がいい対応”のアドバイスも行っています。
●②家庭内の役割バランスを整える
- 家族の中で、引きこもっている子どもだけが特別扱いになっていないか
- 兄弟姉妹の不満や不安が放置されていないか
- 家庭内の空気が「常に緊張」になっていないか
家全体が健全に回る仕組みを取り戻すことで、本人のプレッシャーも緩和されます。
●③“成功体験”を一緒に設計する
- 「部屋から出る」「挨拶をする」「散歩する」など、小さな目標を一緒に達成していく
- 誰かに褒められる機会を意識的につくる
- “本人の存在が価値あるものだ”と実感できる体験を設計する
これらの積み重ねが、「社会との再接続」につながっていきます。
本人の変化を待つのではなく、家庭が“変化しやすい環境”に進化することが、再出発の最大の鍵なのです。
【11. 私たちが動ける理由。秘密裏のサポート体制】
「どこに相談しても動いてくれなかった」
「支援はあるけど、現実には何も変わらなかった」
私たちがこれまで受けてきた相談の多くが、そんな“行き場を失った声”でした。
私たちトラブルなんでも解決屋は、こうした声に応えるために生まれた、
日本でも数少ない“問題解決のために動ける専門チーム”です。
●365日・24時間対応
引きこもりの問題は、いつ何が起こるかわかりません。
深夜や休日にも、親御さんが「限界だ」と感じる瞬間があります。
だからこそ、私たちは常に待機し、必要なときに即対応できる体制を整えています。
●チームでの総合対応
元探偵、心理支援の専門家、教育・福祉経験者など、複数の分野のプロが連携し、
家庭・本人・社会との関係をトータルで再構築します。
調査だけで終わるのではなく、「再スタートまで見届ける」のが私たちのスタンスです。
●徹底した秘密保持と匿名性
依頼者の情報、調査内容、接触記録などはすべて厳重に管理し、
本人にも、周囲にも一切知られずに進行します。
「知られずに動きたい」「記録を残したくない」という方にも対応可能です。
「相談だけしてみたい」「今すぐ動くわけではないけど話を聞いてほしい」
そんな方でも構いません。
私たちは“依頼の前から動き出している”という意識で、親身に対応しています。
引きこもりという深い悩みに、真正面から向き合う覚悟があります。
どうか一人で抱え込まず、私たちに話してください。
あなたのご家庭のために、動けるプロがここにいます。
一覧へ戻る