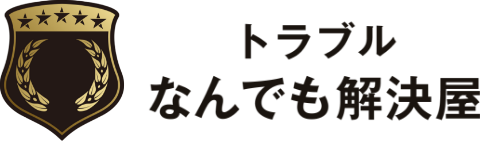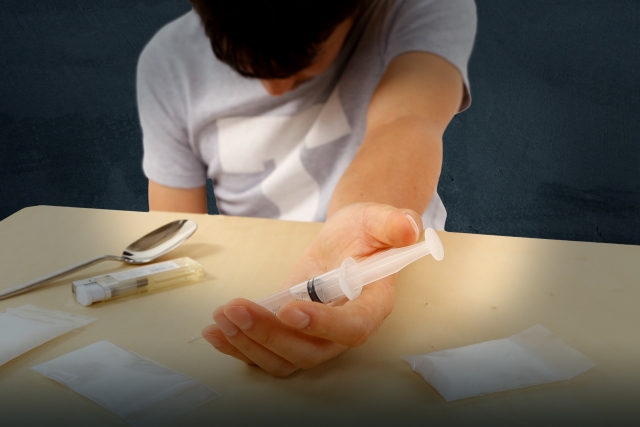2025.04.21
2025.04.21
家族トラブル
お子様に関するトラブル
非行に関するトラブル
子供の薬物使用に親が気づくサインとは

【はじめに】
「まさか自分の子に限って…」
そう思っていた親御さんからの相談が、実は増えてきています。
近年、未成年が関与する薬物問題はSNSやネット経由で静かに広がり、
従来の“非行少年”のイメージとは異なる形で表面化しています。
市販薬の乱用、違法薬物の試し使用、合法ドラッグの入手――
一見真面目な子どもであっても、誰でも巻き込まれる可能性があるのが今の現実です。
本記事では、以下のような内容を専門調査チームの視点で解説します:
- 薬物に関わる子どもの行動パターン
- 親が家庭で気づけるサインや兆候
- 実際に調査で判明した事例とその後の対応
- 学校・警察に頼れないケースでの動き方
- 誰にも知られずに事実を確認する方法
最後に、自力での対処がなぜ難しいのか、そして私たちがどう関われるかについても紹介します。
不安を感じている方にとって、この記事が“冷静に一歩踏み出すための判断材料”になれば幸いです。
 元木
元木
【1. 現代の薬物問題は“別世界の話”ではない】

「薬物」と聞くと、多くの人が“大人の世界”や“裏社会”を連想するかもしれません。
しかし現代の薬物問題は、そんな想像とはかけ離れた場所から始まっています。
特に未成年や学生の間では、「違法薬物」というよりも、“ちょっとした好奇心”や“手に入りやすさ”がきっかけになるケースが多いのです。
実際に、私たちが扱った調査案件でも、子どもが初めて薬物に触れた場所は以下のようなものでした:
- SNSでつながった“先輩”から勧められた
- クラブやイベントで配られたタブレット型の薬
- 友人が持っていた咳止め薬を試した
- 市販薬を組み合わせて“ラリる方法”をネットで見た
- デリバリーアプリを介して“見た目の違う中身”が届いた
このように、入り口はとても“ライト”で、本人の中では「危ないことをしている」という意識が薄いのが特徴です。
特にスマホ1台あれば誰とでもつながれる現代では、
「買う」「受け取る」「試す」までのすべてが親の目をかいくぐって行われるのも珍しくありません。
「薬物なんて別世界の話」
そう思っていた家庭ほど、実際には子どもの手の届く場所に“きっかけ”が存在しているのが、今の現実です。
【2. 子どもが薬物に手を出す理由と背景】

では、なぜ子どもが薬物に手を出してしまうのか?
そこには単なる好奇心だけではない、複雑な背景が潜んでいることが多いのです。
よくあるきっかけや動機として、以下のようなケースが見受けられます:
- 人間関係のストレスや孤立感からの逃避
- 親との不和、家庭内での緊張や抑圧
- 学業や進路への不安、プレッシャー
- トラウマやいじめなどによる自己否定感
- 「自分を変えたい」「強くなりたい」という思い
- 仲間内での“ノリ”や“試し”による軽いスタート
- SNSや動画での“楽しそうな演出”への憧れ
特に思春期の子どもにとって、「自分の居場所がない」と感じたときに、薬物の“一時的な快楽”が強烈な逃げ道になってしまうのです。
また最近では、“依存”という言葉が形を変えて広がっています。
たとえば、
「気持ちが落ち込んだときに市販薬を飲むと楽になる」「学校に行く前に飲まないと落ち着かない」――
これらも立派な薬物依存の初期段階です。
つまり子どもは、「薬物を使っている」という意識がないまま、すでに“やめられない状態”に入っている可能性があるのです。
【3. 薬物使用に見られる初期サインとは】

薬物使用が疑われる子どもには、共通して現れる“微妙なサイン”があります。
しかしそれは、親が見ても一見すると「思春期特有の変化」や「最近ちょっと元気がないだけ」と見過ごされがちです。
以下に、私たちが実際の調査で確認してきた“初期兆候”をまとめました:
●行動面の変化
- 帰宅時間が不自然に遅くなる
- 急に家にいる時間が減る
- 夜中に外出したがる/部屋にこもりがちになる
- 生活リズムが極端に乱れる(昼夜逆転)
●身体的な変化
- 目がうつろ/焦点が合わないことがある
- 顔色が悪い、または目の充血・目の周りのクマ
- 極端な眠気、または異様なハイテンション
- 急な食欲不振または過食
- 汗を異常にかく、手の震えなど
●心理・性格面の変化
- 無気力になる、イライラすることが増える
- 言動が攻撃的になったり、急に優しくなったり波が激しい
- 家族との会話を避けるようになる
- 異常にスマホを気にする/ロックを強化する
●持ち物や部屋の異変
- 見慣れない容器・薬袋・器具のようなもの
- 香水などの匂いでごまかそうとする形跡
- 使い方のわからない道具(スポイト、紙片、ラップなど)
- 急に金遣いが荒くなる
これらのサインは単独では判断が難しいかもしれません。
しかし、複数が同時に見られたときは、早期に事実確認を行うべきタイミングです。
薬物使用は、“見えない場所”で進行していきます。
「何かおかしい」と思ったときに動かなければ、子どもはさらに深いところへと引きずり込まれていきます。
【4. 実際にあった薬物使用調査の事例】

ここでは、私たちが実際に対応した「子どもの薬物使用調査」の中から、特に多かった事例を一部ご紹介します。
プライバシーに配慮し内容は一部変更していますが、現場での調査・対応はいずれも実在の案件に基づいています。
●ケース①:市販薬の過剰摂取とSNSでの取引
依頼者は高校生の息子を持つ父親。「最近やけに眠そう」「急に食事を取らなくなった」ことから違和感を覚えたとのこと。
調査を開始したところ、本人のSNS裏アカウントにて“眠れる薬、1シート2000円”といったやり取りが行われているのを発見。
さらに、自室からは市販の風邪薬や鎮痛剤が大量に発見され、組み合わせによる乱用が明らかに。
本人は「ただの眠剤だから問題ない」と主張していたが、実際には強い依存が形成されていた。
その後、医療機関と連携し治療へ。
親が早期に違和感をキャッチしたことで、取り返しのつかない状態になる前に介入が可能だった。
●ケース②:先輩に誘われた“試し”が常習に
依頼者は中学生の娘を持つ母親。「夜になると部屋の電気を消してスマホをずっと見ている」「急に学校を休むようになった」との相談。
調査を進めた結果、上級生との交流を通じて“リキッドタイプ”の薬物を一度だけ使用。
その後、LINEで定期的にやり取りしていたことが判明。
娘本人は「やめたいけど、断ると写真を出されるかもしれない」と話していた。
こうした“脅し”や“心理的支配”が背景にある場合、本人だけでは抜け出せない状況になる。
最終的には、対象となる上級生との接触を断つための法的措置も視野に入れた対応が行われた。
こうした事例からも分かるように、薬物の問題は“見えにくい”うえに“個人の問題では済まない”複雑な要素を含んでいます。
だからこそ、家庭だけでの対応では限界があるのです。
【5. 薬物がもたらすリスクと家庭への影響】
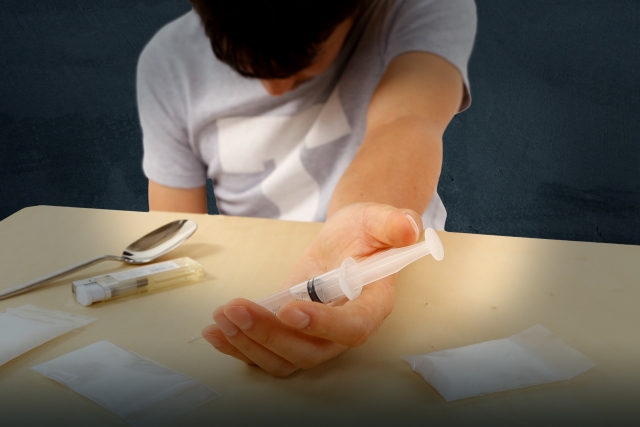
子どもが薬物に関わることで受けるリスクは、単なる身体的なものにとどまりません。
以下のように、あらゆる側面に深刻な影響が広がっていきます。
●本人への影響
- 脳や神経へのダメージ(記憶力・集中力の低下)
- 依存症の進行による精神疾患(うつ・不安障害など)
- 身体の不調(胃腸障害・睡眠障害・ホルモン異常)
- 自己肯定感の喪失と社会的孤立
- 警察沙汰・補導・少年院への送致
●家庭への影響
- 親子関係の悪化(不信感・口論・暴力)
- 家族全体の精神的疲弊
- 兄弟姉妹への悪影響や学業への支障
- 地域や学校との関係悪化(噂・対応の限界)
さらに、薬物の多くは金銭的な継続コストがかかるため、
- 万引き・盗難・買春といった新たな犯罪への拡大
- 家庭内の金品持ち出しや隠し借金
といった“連鎖的リスク”に発展することも珍しくありません。
つまり薬物の問題は、「バレたら終わり」ではなく、「バレなかったからもっと深く進む」ことが本当の恐ろしさ。
放置や様子見が取り返しのつかない結果に繋がることもあるのです。
【6. 市販薬・処方薬でも乱用は起きる】

薬物問題と聞くと、「覚醒剤」「大麻」などの違法薬物を想像する人が多いかもしれません。
しかし、現代の未成年が関わる薬物使用の多くは、“合法的な薬の悪用”から始まっています。
特に多いのが以下のようなケースです:
●市販薬の多剤併用・過剰摂取
- 風邪薬や咳止めを複数種類同時に飲む
- 市販の鎮痛剤を“気分を変える目的”で乱用
- 眠剤代わりに抗ヒスタミン系の薬を摂取
●処方薬の横流し・不正入手
- 親の薬や兄弟の薬を勝手に使用
- “病院でもらったから安全”という誤解
- SNSを通じた処方薬の売買(違法)
●エナジードリンク・サプリの大量摂取
- 覚醒効果を期待して数本一気に飲む
- 組み合わせによる“気分のコントロール”を狙う
これらの行為は、法律的には違法でないケースもありますが、
身体や精神への悪影響は、違法薬物と同様に深刻です。
特に未成年の脳や発達にとっては、少量でもダメージとなり、
将来のメンタルヘルスや人格形成に大きく影響を与えることがあります。
「違法じゃないから大丈夫」とは絶対に言えない――
この事実を、まずは親が知ることが、対応の第一歩です。
【7. なぜ親には相談しにくいのか】

「何かあったら相談してね」――
多くの親御さんがそう声をかけています。
でも実際には、子どもは“本当に深刻なことほど”親に話しません。
特に薬物が関わる場合、それは顕著です。
では、なぜ子どもは親に相談できないのでしょうか?
●怒られる・否定されるという恐怖
薬物=悪いことという認識は、子ども自身にもあります。
だからこそ、「バレたら激怒される」「自分を否定される」という恐怖心から、隠す選択をします。
●“失望されたくない”という気持ち
真面目だった子ほど、「親をがっかりさせたくない」「期待を裏切ったと思われたくない」という心理が強く働きます。
これも、打ち明けられない原因のひとつです。
●そもそも問題だと自覚していない
「ただの咳止めだから」「みんなもやってるから」と、薬物使用を軽く捉えているケースもあります。
この場合、本人の中に“相談するべき問題”という認識がないため、親の前でも自然に振る舞います。
●親子関係が“遠くなっている”
思春期は、親に依存しながらも距離を取りたがる時期です。
もし日常的な会話が減っていたり、スマホが常に壁になっているような状態であれば、子どもにとって「親は敵」になっていることもあります。
つまり、親が「うちの子は何かあれば相談してくる」と思っていても、
実際にはまったく違う心理状態であることが多いということです。
だからこそ、子どもの“表の顔”だけを信じるのは危険です。
裏側をきちんと把握するためには、本人に聞くのではなく、“見えない部分の事実”を丁寧に確認する必要があります。
【8. 学校や警察では対応できない理由】

「もし本当に危ない状況なら、学校や警察がなんとかしてくれるはず」
そう考えて動いた保護者の方も少なくありません。
しかし実際には、こうした公的機関だけでは対応しきれない現実があります。
●学校の限界
- 生徒指導には“証拠”が必要
- プライバシー尊重の原則で、踏み込んだ介入ができない
- 生徒本人が否定すれば、それ以上動けないことが多い
- 薬物の知識や対応マニュアルが不十分な学校も多い
●警察の限界
- “事件性”がないと動けない(=現行犯や被害届がないと調査できない)
- 本人の意思で使用している場合、対応が難しい
- 親の「調べてほしい」という意向だけでは動けない
- “未遂”や“疑いレベル”では介入不可なケースがほとんど
また、最も重要な問題は、“一度公的機関に動いてもらうと、記録が残る”ということ。
これが学校生活や進学、就職に影響することを恐れて、相談をためらう保護者も多くいます。
私たちのもとには、「警察や学校に相談してみたが、結局何もできなかった」
「逆に子どもにバレて関係が悪化した」
という声が多数寄せられます。
だからこそ、まずは“秘密裏に事実を確認する”というプロセスが重要なのです。
【9. 誰にも知られずに事実を確認する方法】

「このまま放っておくのは怖い。でも本人を問い詰めるのも、学校に通報するのも違う気がする」
そんなとき、私たちのような民間の調査機関ができることがあります。
私たちは、親御さんに代わって以下のような方法で、本人や周囲に知られることなく、状況を丁寧に調べます:
●スマホやSNSの使用傾向の分析
- 裏アカウントや怪しいやり取りの特定
- 薬物関連用語・絵文字・隠語の使用チェック
- 時間帯ごとの通信ログや投稿内容の変化
●行動パターンの観察・尾行調査
- 不自然な外出先や滞在時間の確認
- 接触している人物の身元確認
- 特定の場所(クラブ・公園・集合場所)への出入り記録
●持ち物や環境調査(親の協力のもと)
- 部屋の中やバッグに怪しい道具があるか
- 市販薬や処方薬の異常な減り方の確認
- 受け取り物(荷物・現金・ギフト)の特定
こうした調査を通じて、「何もない」とわかることもあります。
でも逆に、「今すぐ動くべき状況だ」と判明することも、決して珍しくありません。
重要なのは、“確かめてから動く”という順番です。
感情的に動いてしまえば、子どもとの信頼関係を壊す可能性もあります。
だからこそ、冷静に状況を把握できる第三者の介入が、最も効果的なのです。
【10. 発覚後に必要な対応と再発防止策】

薬物使用の事実が明らかになったあと、親御さんがもっとも悩まれるのは「この先、どうすればいいのか」という点です。
実際、発覚後の対応によっては、状況が良くも悪くも大きく変わります。
ここで大切なのは、“怒る”ことでも“監視する”ことでもなく、建設的に関係を再構築し、再発を防ぐ仕組みをつくることです。
具体的には以下の3つのステップが重要です:
●①事実と向き合う環境づくり
親のショックや怒りは当然ですが、子どもにとっては「責められる」「信頼を失った」と感じると、ますます心を閉ざします。
まずは感情を抑え、「どうしてそうなったのか」を一緒に確認する姿勢が必要です。
●②専門的サポートの活用
薬物使用の背景には、ストレスや依存、トラウマ、家庭環境など様々な要因が潜んでいます。
そのため、親だけでの対応では限界があることも多く、心理カウンセラーや医療機関との連携が不可欠になるケースもあります。
また、当社でも調査後の心理ケアや進路相談のフォローまで対応しています。
●③日常への“信頼と監督”のバランス調整
再発を防ぐには、行動管理と信頼回復の両立が必要です。
たとえば、スマホの使い方の見直し、金銭管理、外出先の記録などを行いながら、
「必要以上に縛らない」対話の工夫も求められます。
大切なのは、薬物を使ってしまった“過去”ではなく、今後をどう築くかです。
一度失った信頼も、時間と対応で取り戻せます。
親と子ども、両方の視点で動ける体制こそ、私たちが提供できる価値のひとつです。
【11. トラブルなんでも解決屋だからできる、秘密裏の対応と本気のサポート】
「誰にも相談できない」「こんなこと、どこに頼めばいいのかわからない」
私たちが日々受け取っているご相談の多くは、そうした“人に言いづらい問題”ばかりです。
薬物使用もそのひとつ。家庭内で抱え込んでしまい、状況が深刻化してから動き出すケースも少なくありません。
トラブルなんでも解決屋では、こうした問題に専門チームで対応しています。
薬物調査のプロだけでなく、必要に応じて
- 心理カウンセラー
- 教育・進路アドバイザー
- 弁護士や法務の専門家
- IT・SNS調査の技術者
など、複数の専門家が連携して、“問題の根本”から動きます。
また、私たちは365日・24時間体制での対応が可能です。
トラブルに「営業時間」はありません。
不安な夜、突然の発覚、家族との対話が崩れそうな瞬間――
そんなとき、すぐに動ける体制を整えています。
そして何より、調査も対応もすべて秘密裏に進行します。
お子様本人にも知られることなく、学校・職場・第三者に情報が漏れることはありません。
調査結果の取り扱いにも細心の注意を払い、信頼関係を壊さない“ギリギリのライン”でサポートします。
「どこにも頼れない」そう感じたときこそ、私たちを思い出してください。
他のどこにもない解決力と、依頼者に寄り添う本気の姿勢で、未来を守るお手伝いをします。
まずはご相談ください。秘密厳守・無料でお話を伺います。
一覧へ戻る