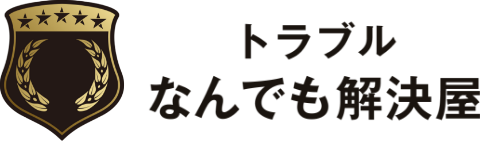2025.05.02
2025.05.02
法人トラブル
社内調査
社内のパワハラ問題と経営者が取るべき対応策

【はじめに】
「うちの会社にはパワハラなんてない」――
そう思っていた企業こそ、水面下で深刻な問題を抱えていることが多いのが現実です。
社員からの声が上がる前に、
- 離職者が続く
- 職場の空気が悪くなる
- 業務ミスや人材流出が続く
といった“見えにくいサイン”が出ていることも少なくありません。
本記事では、
- 社内パワハラの見抜き方と兆候
- 部下が声を上げられない理由
- 会社として放置してはいけない理由
- 調査・証拠取得・社内対策の方法
を、企業リスク管理の専門視点から解説します。
 元木
元木
【1. パワハラが企業経営に与える本当のダメージ】

パワハラは単なる「社内の人間関係トラブル」ではありません。
放置すれば、企業そのものの信頼・収益・人材すべてを蝕む深刻な経営リスクに発展します。
●パワハラが引き起こす実際の被害:
- 有能な人材の早期退職(本音は語られず、円満退職に見える)
- 社内の空気の悪化によるモチベーション低下・生産性の著しい低下
- SNSや口コミ、転職サイトでの評判悪化
- 労働基準監督署への通報→行政指導や調査
- 労災・損害賠償請求・訴訟リスク(1件で数百万円〜の賠償例も)
- メディア報道によるイメージダウン(特に上場企業・有名企業は致命的)
そして何より怖いのは、被害が“見えづらい形”で広がること。
社員は簡単には声を上げず、「辞めて終わり」が当たり前になっているケースも多く、
経営層が把握した時にはすでに手遅れ、という事例が後を絶ちません。
【2. パワハラの種類と“見えない加害者”の特徴】

パワハラ=怒鳴る・暴言を吐く――そんな“わかりやすい加害者”だけではありません。
実際は、もっと巧妙で表に出にくい形で進行しているケースが多いのです。
●主なパワハラの種類:
- 精神的な攻撃(無視・暴言・威圧・人格否定)
- 過大な業務指示(明らかにこなせない量を与える)
- 過小な業務(仕事を与えない・外す・孤立させる)
- 私的なことに過剰に踏み込む(恋愛・家庭・思想など)
- 業務妨害(会議で発言を封じる・成果を横取りする)
- 退職強要や「圧力」による辞職誘導
●“見えない加害者”の特徴:
- 上司・古株・ベテラン社員など社内での影響力が強い
- 表向きは温厚・指導熱心に見える
- 部下が「嫌われたら終わり」と思っている
- 他の社員も黙認していて“空気が出来上がっている”
- 数字は出しているため、管理職や経営者が擁護してしまう
このように、“実力者”や“結果を出す人間”ほど見落とされがち。
「あいつはそんなことするはずがない」ではなく、「可能性を疑う視点」が必要です。
【3. 被害者が声を上げない“沈黙の構造”】

なぜ多くのパワハラは、発覚が遅れるのか?
それは、被害者が「相談できない空気」に押しつぶされているからです。
●被害者が沈黙する理由:
- 上司・先輩に逆らえないという構造的上下関係
- 「言ってもどうせ変わらない」という諦め
- 他の社員も黙っているから、自分だけ言いづらい
- 報復人事や評価への影響を恐れている
- 相談窓口や経営層との距離が遠く、機能していない
- 過去に相談しても「我慢しろ」で済まされた経験がある
この“沈黙の積み重ね”が、
といった “数値化できない損失” となって企業に跳ね返ってくるのです。
パワハラは「声が出たときには被害が限界を超えている」と考えるべき。
沈黙の中にこそ、最大のリスクが隠れているのです。
【4. 離職・生産性低下・内部崩壊…放置の代償】

パワハラを見て見ぬふりした結果、企業がどうなるか。
最も多いのは「社員が静かに辞めていく」という形の損失です。
●よくある“放置の末路”:
- 何も言わずに辞める若手が続出→人材不足に
- 有望な社員ほどストレスに敏感で、早く見切りをつける
- 残った社員は萎縮して意見が出なくなる
- 「あの部署に異動したら終わり」と社内に暗黙の了解が広がる
- 優秀な中堅が転職し、競合や外部にノウハウが流出
- クレーム処理や内部告発が増え、マネジメントが疲弊
これらは短期的には「問題なく回っているように見える」ため、経営層も気づきにくい。
しかし中長期で見ると、会社全体の“地盤沈下”が進んでいることに気づくはずです。
パワハラは「訴えられるかどうか」の問題ではなく、
企業の根幹を静かに壊していく“目に見えない崩壊因子”だと理解する必要があります。
【5. 経営者が見逃しがちな“兆候とサイン”とは】

経営層がパワハラに気づけない最大の理由は、
現場と距離があるため、“兆候”を見逃してしまうからです。
●見落とされがちなサイン例:
- 毎朝の出社がギリギリ、もしくは体調不良が多い社員が増えた
- ある特定の部署だけ離職率が高い
- 社員が上司の前で不自然に黙る/顔色をうかがっている
- 評価は高いのに社内で浮いているリーダーがいる
- 社内SNSやチャットのやりとりが異様に短文・冷たい
- 「話しかけづらい空気」「チームで飲みに行かない」などの距離感がある
こうした“小さな変化”は、現場にいなければ気づけません。
だからこそ、
経営者が意識して「空気」を読み取る努力が必要になります。
あるいは、外部の視点を入れて初めて見えてくることも多いのです。
【6. 社内調査でできること、できないこと】

「社内アンケートを実施したから大丈夫」
「人事に報告がないから問題ない」
――それ、本当にパワハラを把握できていますか?
●社内調査の限界:
- 加害者が管理職や幹部だった場合、誰も本音を書けない
- 形式的なアンケートでは“見てる側”の目を意識した回答になる
- 聞き取り調査があっても「報復が怖いから話せない」
- 被害者自身が「自分の問題」として処理しているケースも多い
つまり、社内調査は「動き出した証拠」が残るだけで、
実態把握はできていないことが多いのです。
社内でできることには限界があります。
パワハラが“疑われる”段階から、
社外の第三者が冷静かつ中立に事実を把握することが必要になるのです。
【7. 第三者による聞き取り・調査の必要性】

社内調査には限界がある――
だからこそ、パワハラの実態把握には社外の第三者による中立的な調査が有効です。
●第三者調査の強み:
- 社員が“本音”を話しやすい(守秘義務・匿名性が確保される)
- 関係者の関係性・背景も含めたヒアリングができる
- 加害者が社内で影響力を持っていても調査が進められる
- 記録に残る報告書として活用できる(人事判断・法的対応にも使える)
- 感情論ではなく“客観的な事実”として経営判断に落とし込める
特に、被害者が「社内に言えない」空気の中にいる場合、
外部の第三者が聞き手になることで、ようやく本当の声が表に出てきます。
また、加害者が意図的に隠している・演技しているケースでも、
外部からの観察で矛盾点が浮かび上がることがあります。
「怪しいけど、決定打がない」
「社内ではこれ以上動けない」
そんなときこそ、第三者の調査力が真価を発揮します。
【8. パワハラが明るみに出た後の対応方法】

仮にパワハラが確認された場合、経営者としては感情に流されず、正しく対処することが最重要です。
●よくある失敗パターン:
- 加害者を急に解雇→報復的だと捉えられ、トラブルが二次炎上
- 被害者の保護が曖昧なまま、社内に戻してしまう
- 「注意しておいたから大丈夫」として対応を終わらせる
- 社内に「パワハラの事実があった」と正式に伝えない(隠蔽と捉えられる)
●望ましい対応ステップ:
- 外部調査結果をもとに、事実確認・証拠を整理
- 加害者への正式なヒアリング・処分内容の検討(就業規則・法的観点を含む)
- 被害者の意向を聞いた上で、安全な職場復帰や配置転換を検討
- 社内への説明(必要最小限かつ適切に)
- 相談体制の再構築と、再発防止策の策定
社内の風土に関わる問題だからこそ、
経営層の姿勢が全体に与える影響は大きいのです。
「パワハラを放置しない会社である」と示すことが、信頼回復の第一歩になります。
【9. 職場の秩序と信頼関係を守るために必要な視点】

パワハラは一部の人間だけの問題ではなく、
職場全体の“空気”と“信頼”を壊すリスクをはらんでいます。
●放置すれば崩れる3つの秩序:
- 上下関係の健全性
→ 上司と部下が建設的に対話できなくなる
- チームワークの信頼
→ 誰かが困っていても「関わらない」が普通になる
- 経営層への信頼
→ 「どうせ経営者は守ってくれない」と思われる
企業文化がそうなってしまえば、
どれだけ制度や人材が整っていても、パフォーマンスは上がりません。
だからこそ、
パワハラの問題は「労務管理」ではなく、
“組織の空気を守る戦い”でもあります。
そしてそれは、
「社員の声に耳を傾ける姿勢」ではなく、
「声が出ないときに気づけるかどうか」で決まります。
【10. 私たちにできること。パワハラ調査と再発防止のための支援体制】

「たぶん問題ないと思う」
「証拠がないからどうしようもない」
――そうして放置されたパワハラが、後になって企業を深く傷つける。私たちは、その現場を何度も見てきました。
トラブルなんでも解決屋では、
社内で声を上げづらいパワハラ問題を“誰にも知られずに調べる”プロの調査体制を整えています。
●対応可能な調査・支援内容:
- 社内で疑いのある人物の言動記録(張り込み・聞き取り)
- 部署内の空気や孤立している社員への接触・実態把握
- 被害者側の意向や心理状態のヒアリング(外部だから話せる本音)
- 加害者が表向きには取り繕っている場合の裏付け調査
- 就業規則や法的観点からの処分方針のアドバイス
- 再発防止のための社内構造の見直し支援
調査は完全非公開で行い、
- 社員にバレない
- 加害者に悟られない
- 経営判断に必要な「証拠」と「状況整理」をご提供します
「うちには関係ない」と思われていた企業ほど、
後から「もっと早く相談していれば…」と後悔されています。
パワハラは、沈黙の中で進行します。
誰も言ってくれないなら、私たちが調べます。
365日・24時間、緊急対応も可能です。
社内に言えない悩みこそ、外部の専門家に任せてください。
まずは一度、匿名でも結構です。静かにご相談ください。
一覧へ戻る